【注目の裁判例】<成田国際空港事件。京都地判令和7年3月27日>
弁護士田村裕一郎です。
今回、TITメルマガ2025年8月号では、定年前退職を必須とした、継続雇用制度が有効か、を解説します。
結論としては、企業は、このような制度を採用する場合、メリット及びデメリットを理解した上で採用すべき、というものです。
よりわかりやすい情報を取得したい方は、本記事のみならず、下記のYouTube動画も、ご視聴下さい。
裁判例の内容
裁判で争点になった点を、以下、ご紹介します。
争点(1)(被告における定年制及び本件再雇用制度が高年法8条及び9条に反するか。)について
(1)原告は、高年法8条及び9条の規定内容からすると、高年法9条1項2号の継続雇用制度は、現に定年まで雇用されている労働者が希望すればその定年退職後も引き続き雇用される制度であることを要するとした上で、被告における定年制及び本件再雇用制度では65歳までの継続雇用を希望する場合は定年前の58歳で退職せざるを得ないから、実質的には58歳を定年とするものであり、全体として高年法8条及び9条に反する旨を主張する。
(2)しかしながら、高年法における「定年」とは、労働者が所定の年齢に達したことを理由として自動的に又は解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度であると解されるところ、被告の従業員は本件再雇用制度を利用せずに60歳で定年退職することを選択することもできるから、本件再雇用制度を利用する場合に58歳で退職する必要があることをもって、被告が定年を58歳と定めたとはいえない。
(3)また、以下のとおり、高年法9条1項2号の継続雇用制度が現に定年まで雇用されている労働者が希望すればその定年退職後も引き続き雇用される制度であることを要するともいえない。
高年法8条が、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は「60歳を下回ることができない。」として同条の予定する定年制の内容を一義的に規定しているのに対し、高年法9条1項2号の継続雇用制度については、条文の文言上、制度の内容を一義的に規定せず、多様な制度を含み得るものとなっている。また、高年法9条の改正の基礎となった労働政策審議会の建議においても、年金支給開始年齢までの雇用の確保を進める一方で、経済社会の構造変化等が進む中で厳しい状況が続く企業の経営環境等を考慮すれば65歳までの雇用確保の方法については個々の企業の実情に応じた対応が取れるようにするべきである旨が指摘されている(前記2(1)イ・ウ)。これらのことからすれば、高年法9条1項は、同項2号の継続雇用制度の具体的な内容については、65歳までの安定した雇用の確保という同項の目的(同項柱書)に反しない限り、各事業主がその実情等に応じて定めるところに委ねる趣旨であると解される。そして,定年退職後に引き続いて雇用される制度としなければ65歳までの安定した雇用の確保という同項の目的に反するということはできない。そうすると、同項2号の継続雇用制度が、現に定年まで雇用されている労働者が希望するときはその定年退職後に引き続き雇用される制度であることを要するということはできない。
以上によれば、本件再雇用制度を利用する場合に58歳で退職する必要があることをもって、実質的に58歳を定年と定めたものとはいえず、高年法8条及び9条に反するということはできない。
(4)この点につき、原告は、高年法9条1項2号が、継続雇用制度を「その定年後も引き続いて雇用する制度」としていることから、継続雇用制度は、定年で退職した労働者を引き続き雇用する制度であることを要する旨主張する。しかしながら、上記規定内容は、「定年と定められた年齢に達した後も引き続いて雇用する制度」と解することもできるのであり、既に説示した同項の趣旨からするとそのように解することが合理的である。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
争点(2)(本件再雇用制度が高年法9条1項に反するか。)について
(1)原告は、本件再雇用制度は、定年まで雇用されている労働者を定年退職後も引き続き雇用する制度であることを要するとして、本件再雇用制度を利用する場合に定年前の58歳で退職する必要があることが高年法9条1項に反する旨主張するが、この主張に理由がないことは、前記3において説示したところから明らかである。
(2)原告は、本件再雇用制度において定年前の58歳の退職時から労働条件が大きく引き下げられることが高年法9条1項2号に反する旨主張する。
本件再雇用制度においては、再雇用後の年収が、〔1〕退職時から60歳の誕生日の属する月の末日までは退職時給与(退職時の基本給及び賞与)の約60%、〔2〕その翌月から63歳の誕生日の属する月の末日までは退職時給与の約50%、〔3〕その翌月から65歳の誕生日の属する月の末日までは退職時給与の約40%とされており(前記第2の2(4)カ)、原告の基本給及び賞与(職能給19万4700円、役割給2万円、育成給20万0800円、令和4年6月及び同年12月の賞与各67万9861円)を基礎として試算すると、退職時給与は年634万5722円であり、前記〔1〕の期間の年収は約380万円、前記〔2〕の期間の年収は約320万円、前記〔3〕の期間の年収は約250万円となる。
しかしながら、前記3(3)において説示したとおり、高年法9条1項は、同項2号の継続雇用制度の具体的な内容については、65歳までの安定した雇用の確保という同項の目的に反しない限り、各事業主がその実情等に応じて定めるところに委ねる趣旨であると解される。
そして、本件再雇用制度は65歳までの継続雇用を前提とするものであり、定年後の高齢者の雇用は事業主に相応の負担を生じさせるものであることからすれば、事業主が65歳までの継続雇用を前提に定年前の一定の時期から労働条件を低下させることをもって不合理であるということはできない。また、被告の職員で組織される労働組合がこのような労働条件の引下げを伴う本件再雇用制度を承諾している上(前記2(2))、原告が本件再雇用制度を利用した場合の年収の低減の程度からみても、本件再雇用制度における労働条件の引下げが安定した雇用の確保という高年法9条1項の目的に反するということはできない。
これらのことからすると、本件再雇用制度において定年前の58歳の退職時から労働条件が引き下げられることをもって、高年法9条1項に反するということはできない。
(3)原告は、労働者が57歳の時点で本件再雇用制度の利用を希望する旨の申請をしなければ、その後、定年に達するまでに継続雇用を希望しても引き続き雇用されることはないことが高年法9条1項に反すると主張する。
しかしながら、前記3において説示したとおり、高年法9条1項は、同項2号の継続雇用制度の具体的な内容については、65歳までの安定した雇用の確保という同項の目的に反しない限り、各事業主がその実情等に応じて定めるところに委ねる趣旨であると解される。そして、本件再雇用制度は65歳までの継続雇用を前提に58歳以降に労働条件を引き下げて雇用を継続する制度であり、この制度が高年法9条に反するものでないことは前記(2)に説示したとおりである。そうすると、本件再雇用制度による雇用が58歳から開始される以上、57歳の時点で本件再雇用制度の利用を選択させることには必要性及び合理性が認められる。したがって、57歳の時点で本件再雇用制度の利用を希望する旨の申請を要することが高年法9条1項の目的に反するということはできない。
以上によれば、57歳の時点で本件再雇用制度の利用を希望する旨の申請を要することをもって、本件再雇用制度が高年法9条1項に反するということはできない。
(4)原告は、本件再雇用制度を選択した従業員について、最終雇用期限を63歳になって初めて迎える6月30日とする運用がされているとして、本件再雇用制度は高年法9条1項に反すると主張するが、本件再雇用制度を選択した従業員について、最終雇用期限を63歳になって初めて迎える6月30日とする運用がされていることを認めるに足りる証拠はない。
争点(3)(本件再雇用制度が高年法の趣旨に反するか)
(1)原告は、労働者が本件再雇用制度を利用する場合には、定年退職する場合と比べて5年長く就労するにもかかわらず、総収入の差はわずかであり、原告の場合で304万6525円増えるにとどまるのであって、上記の差額を5年間の収入とみると最低賃金を大きく下回る著しく廉価な賃金で労働者を5年も働かせるものといえるから、本件再雇用制度は、労働者が合理的には選択し難い制度であり、高年法の趣旨に反すると主張する。
(2)しかしながら、前記3(3)において説示したとおり、高年法9条1項は、同項2号の継続雇用制度の具体的な内容については、65歳までの安定した雇用の確保という同項の目的に反しない限り、各事業主がその実情等に応じて定めるところに委ねる趣旨であると解される。
そして、前記4(2)に説示した本件再雇用制度を利用した場合の賃金の低下の程度や被告の職員で組織される労働組合がこのような労働条件の引下げを伴う本件再雇用制度を承諾していることからすると、本件再雇用制度における賃金が65歳までの継続雇用を希望する労働者においておよそ選択し難い不合理なものであるということはできない。
この点について、原告は、定年退職する場合との差額を5年間の収入とみて、最低賃金を大きく下回る著しく廉価な賃金で労働者を5年も働かせるものであり、労働者が合理的には選択し難い制度であると主張する。しかしながら、本件再雇用制度は、65歳まで雇用が継続されることを前提に定年前の58歳の退職時以降の労働条件を引き下げるものであり、雇用契約が存在する期間が異なるにもかかわらず単純に定年退職する場合と賃金総額を比較してその差異を5年間の賃金として著しく低額であると評価するのは相当でない。
争点(4)(本件再雇用制度の導入が労働契約法10条により労働契約の内容にならないか。)について
原告は、本件再雇用制度のうち、定年前に退職し60歳までの労働条件を不利益に変更する部分は、就業規則の不利益変更に該当すると主張する。
しかしながら、本件再雇用制度の導入は、65歳までの継続雇用が可能となる措置を選択肢として設けるものにすぎず、被告の従業員は本件再雇用制度を利用しないこともでき、その場合には、本件再雇用制度の導入前と同じく、労働条件の変更を伴わず、60歳に達したときに定年退職することとなる。そうすると、被告の従業員は、その選択によって、本件再雇用制度の導入前と同じ利益を得ることができるから、就業規則を変更して本件再雇用制度を導入したことが就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当するとはいえない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
争点(6)(高年法の規定又は趣旨に反する本件再雇用制度を定めたことが不法行為を構成するか。)について
原告は、被告が高年法8条及び9条又は高年法の趣旨に反する本件再雇用制度を定めたために原告が60歳で定年退職となり60歳以降も就業して賃金を得る権利又は継続雇用制度の合理的運用により65歳までの安定的雇用を享受することができるという法的保護に値する利益を侵害されたとして不法行為が成立する旨主張する。
しかしながら、本件再雇用制度が高年法8条及び9条又は高年法の趣旨に反するものでないことは既に説示したとおりであるから、原告の主張は理由がない。
企業はどうすべきか。
1、まず、今回の裁判例は、1審です。これが控訴されているかどうか、は必ずしも判然としません(2025年8月23日現在)。そのため、今後の上訴審(もしあれば)に注意すべきです。
2、次に、労働条件の不利益変更に注意すべき、です。この裁判例では、高年法の改正に合わせて、「新しく」再雇用制度を導入しています。そのため、労働条件の不利益変更の論点が出てきません。
しかし、本記事を読まれている企業は、おそらく、既に、何らかの継続雇用制度を導入されていることが多いと思われます。
そうすると、既存の継続雇用制度を変更することになりますので、仮に、定年前退職を必須とする継続雇用制度を導入する場合、労働条件の不利益変更に該当する可能性が高いです。
そのため、労働条件の不利益変更に該当しないよう、注意すべきです。
3、さらに、高年法に違反しないか、も注意すべきです。youtube動画で詳細な解説をしていますが、裁判では、高年法に反しないか、が厳しく争われます。制度の1つ1つの事項(年齢設定、賃金減額設定、応募期限など)について、細心の注意を払って、決定していくべきです。
4、加えて、同一労働同一賃金にも、注意すべきです。本裁判例と類似する制度を採用した場合、「65歳までの雇用を選択する」社員が出てきます。この場合、同一労働同一賃金に違反しないよう、賃金や業務内容などを決定する必要があります。
5、最後に、組合等の意見にも、注意すべきです。過半数を占める労働組合や、(労働組合がない場合)過半数代表者、個々の社員がどのような意見を持っているのか、にも、留意すべきです。
★上記を含む詳細については、YouTube動画をご視聴ください。
厚労省の(当時の)見解
厚労省の(当時の)見解は、次のとおりです。
厚労省は、現在、「高年齢者雇用安定法Q&A」(令和7年3月31日改訂)(令和7年4月1日適用)を公表しており、その中には、下記は、含まれていません。もっとも、「高年齢者雇用安定法Q&A」(令和7年3月31日改訂)以前の、高年齢者雇用安定法Q&Aにおいて、下記を公表しておりましたので、下記は、その中からの抜粋です。
- Q1-5:例えば55歳の時点で、
①従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
②55歳以降の労働条件を変更した上で、65歳まで継続して働き続ける
のいずれかを労働者本人の自由意思により選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。 -
A1─5:高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。
- Q1-6:例えば55歳の時点で、
①従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
②55歳以降の雇用形態を、65歳を上限とする1年更新の有期労働契約に変更し、55歳以降の労働条件を変更した上で、最大65歳まで働き続ける
のいずれかを労働者本人の自由意思により選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。 -
A1─6:高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。
なお、1年ごとに雇用契約を更新する形態については、高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、65歳までは、高年齢者が希望すれば、原則として契約が更新されることが必要です。個々のケースにおいて、高年齢者雇用安定法の趣旨に合致しているか否かは、更新条件がいかなる内容であるかなど個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。
動画解説
本記事に関連する動画解説を希望される方は、下記YouTubeをご視聴下さい。
補足:参考情報
1、今後、新しい情報が入れば、アップデートしたいと思っています。
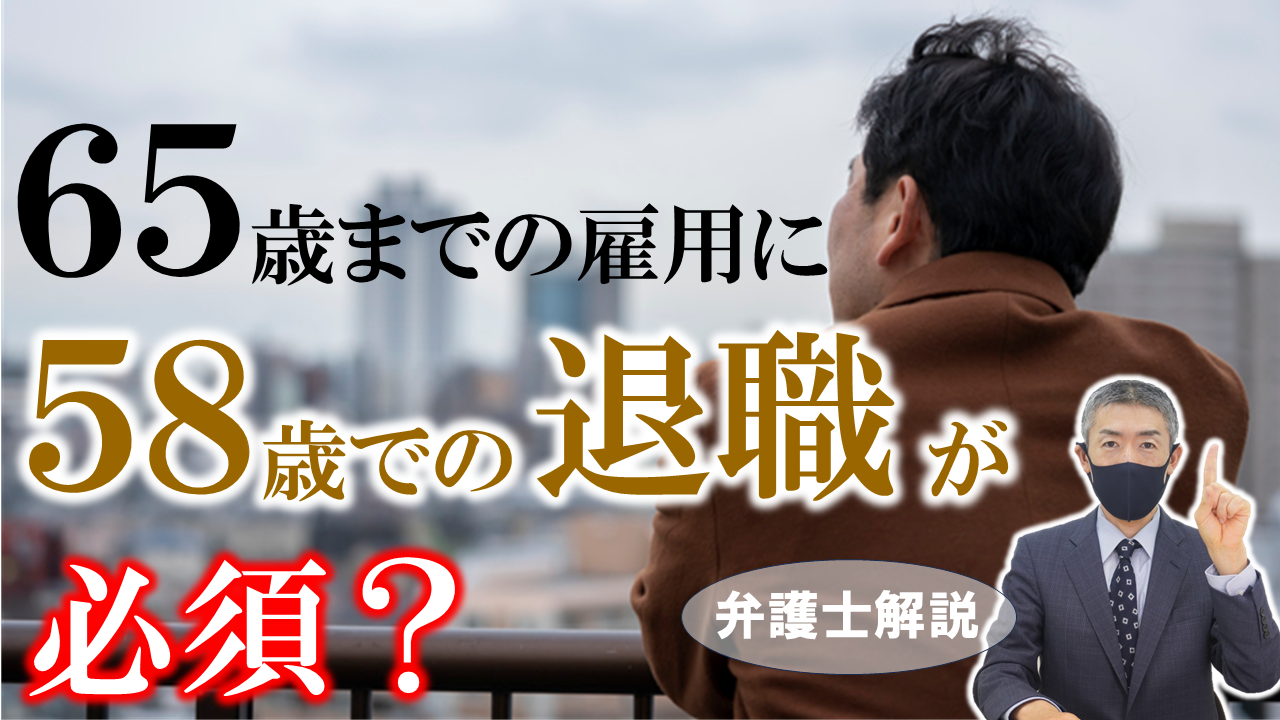

コメント